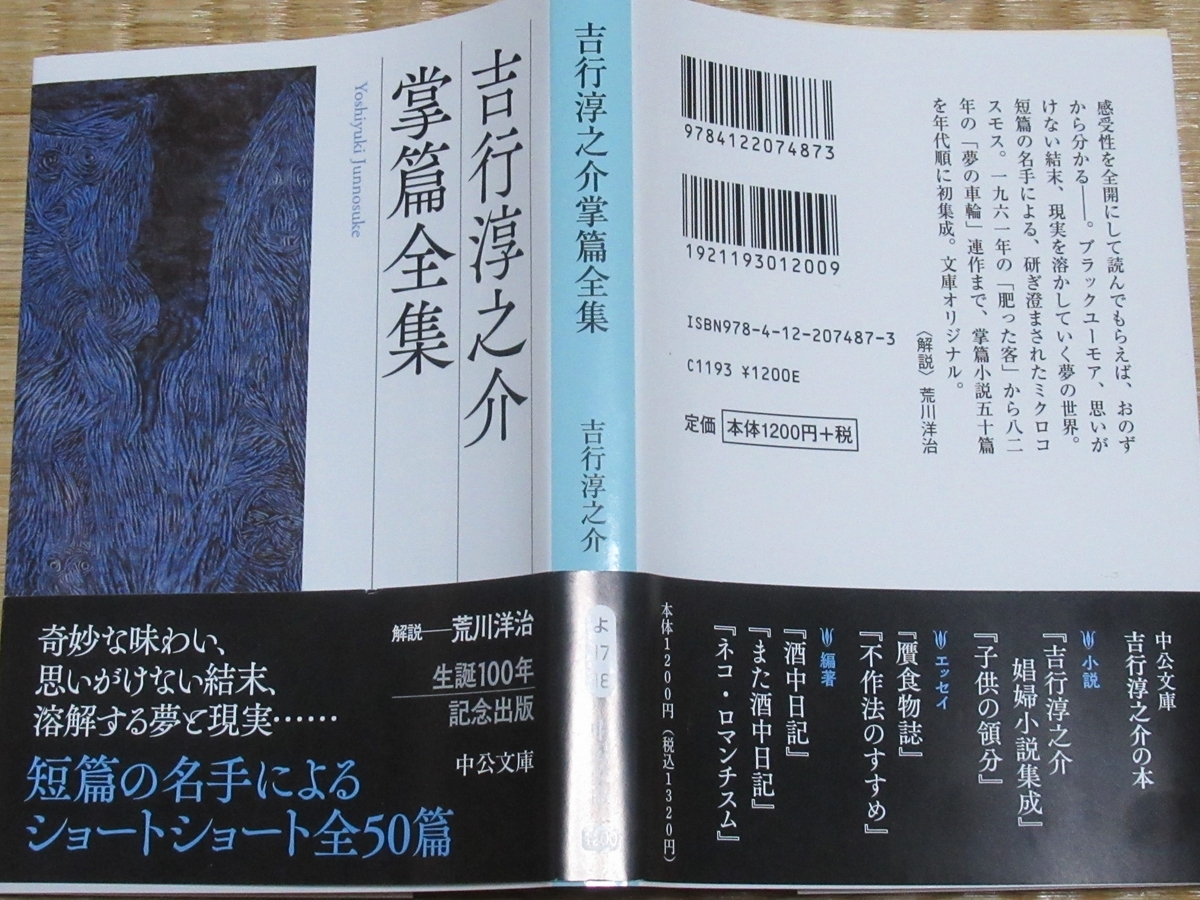今村夏子『むらさきのスカートの女』
今日は読書の話題です。最近読んだ本2冊の感想。
1冊目は今村夏子の『むらさきのスカートの女』。数年前の芥川賞受賞作だが、なんとなく気になる題名で、一度読んでみようと思っていた。文庫本で160ページくらいの短めの長編(中編)だ。
読む人によって評価が結構分かれる小説かもしれないが、私はとてもおもしろかった。相性のいい作品だった。
主人公の「わたし」(女性)は、家の近所に住んでいる謎めいた「むらさきのスカートの女」のことが気になり、いつも周囲にいて様子を観察している。「むらさきのスカートの女」はボロアパートに一人暮らしで、身なりにも構わず、勤め先もすぐに変わる。働いていないときには公園のいつも同じベンチに座り、子供たちにからかわれている。普通に考えれば何の魅力もない女なのだが、「わたし」はその女に執着し、どうにかして友達になりたいと思い、いろいろと画策する。そして「むらさきのスカートの女」は、ついに「わたし」と同じ職場で働くようになる。
こうやってあらすじを書き出してみても、作品の雰囲気はなかなか伝わらない。不思議な世界なのだ。そもそも、「わたし」がなぜその女にそこまで執着するかが、一切示されずに話が進んでいく。また、「わたし」が常に彼女の周囲につきまとっているのに、彼女はそれに気づかない。そういった意味で、一人称で書かれている小説なのだが、主体である「わたし」の存在の方が謎で、実体が分からない。そして読み進めていくにつれて、その違和感、あるいは不安な感じが膨れ上がり、「わたし」の異常さが際立ってくる。
純文学として、色々な分析の仕方はあるだろうが、私はこの作品は読み物としておもしろかったし、文も平易だが惹きつけられる文章で、上手いと思った。あちらこちらにクスっと笑える箇所があるのもよかった。
それから、文庫本の作品の後には、作者のエッセイが数編収録されていたのだが、まさに作者の人物像と作品のイメージがぴったり合致していた。ただし、作家はエッセイに等身大の自分のことを書くとは限らないので、本当かは分からない。
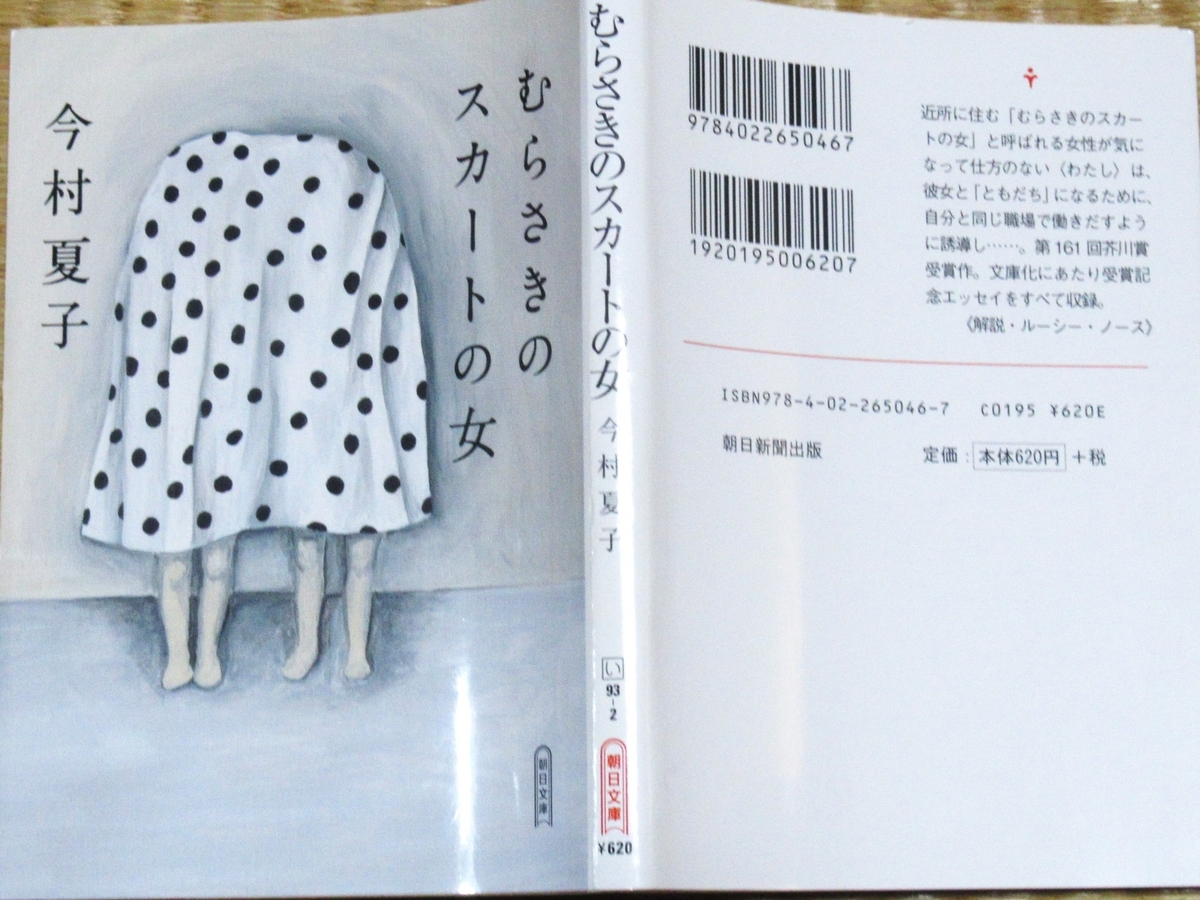
吉行淳之介『吉行淳之介掌篇全集』
吉行淳之介の作品は、小説もエッセイも昔よく読んだ。わが家の本棚にも、ちゃんと数えたことはないが、30冊ほどあるだろう。すでに亡くなってから30年たつが、昔ながらの文士という呼び方がしっくりとくる人だ。書店の文庫本の棚には、その時期に売れている作家の本がずらりと並んでいるが、吉行淳之介もそういった作家のひとりだった記憶がある。
本屋で『吉行淳之介掌篇全集』という文庫本が新刊で出ていたので、手に取って目次を見ると、読んだことのある作品も半分くらいあるが、初めて見る題名も多かったので思わず買ってしまった。
ところで、「掌編小説」の定義だが、短編より短い、原稿用紙10枚以内くらいの小説を指すというのが一般的だ。「ショートショート」との違いだが、私のイメージでは、古くは星新一に代表されるような、アイデアとプロットのおもしろさで読ませる作品がショートショートで、文学的な色合いが強いものが掌編という漠然とした捉え方があった。吉行淳之介の作品は、その意味では「掌篇」寄りで、「ショートショート」ではないのだが、この文庫本の帯には「短篇の名手によるショートショート全50篇」とあったので、同じようなものと考えていいのかと思ったのだった。
読んだ感想は、作者自身も「この種の作品は、作者と読者の呼吸が合わなくては、さぱり分からなくなる」と書いているように、しっくりくるものもあれば。そうでないものもあった。作品は発表された年代順に並んでいるが、比較的早い時期の作品の方が好きなものが多かった。上げていくと『目覚時計』『紺色の実』『蠅』『古い家屋』『扉の向こう』『蛾』など。最後の『夢の車輪』に収録されていた12編は、夢をモチーフにした作品だが、私の感性が不足しているのか、うまくついていけなかった。ただ、作者自身、作品の世界に自分の感覚が合う人に味わってもらえればそれでいいという姿勢で書いているから、それはしかたないのだろう。